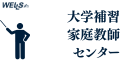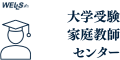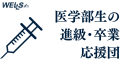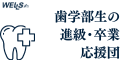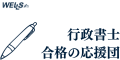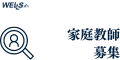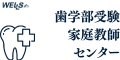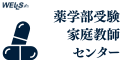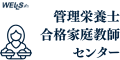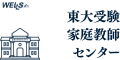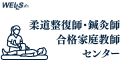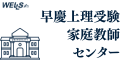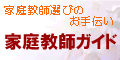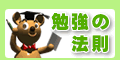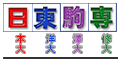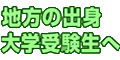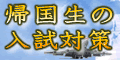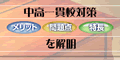受験指導のプロがそっと教えるテクニック— 国内研究で見る効果的反復の仕組み
教材を何冊も並行して“通すだけ”ではなく、1冊を深く回して「理解を定着」させる人が、確実に学力を伸ばしています。国内の教育・記憶研究にも、その学習設計が有効であることが示されています。
ここでは、日本のエビデンスをベースに、「教材をやり尽くす」ための考え方と実践ポイントを整理します。
なぜ「やり尽くす」が効くのか:日本の研究から見る理論的裏付け
反復と記憶定着
大阪教育大学の報告によれば、新しく覚えた情報は「短期記憶」から「長期記憶」へ移行する際、復習の回数が多く、印象が強い情報ほど定着しやすいとしています。f.osaka-kyoiku.ac.jp
つまり、何度も教材・問題に触れることが、長く覚えておくために有効だということです。
間隔をあけた反復の効果
関西大学などの研究では、「復習の間隔を段階的に広げる(拡張分散学習)」ことで、より長期の記憶保持に有利であるとの報告があります。関西大学
教材を「ただ回す」のではなく、時間をあけて再挑戦することが鍵です。
神経レベルでのメカニズム
ある神経科学系の研究では、反復学習を継続すると、脳内の転写因子(例えば CREB, c-fos)が活性化し、“記憶が残る”細胞集団が形成されるというメカニズムが明らかにされています。医学研
学習の“質”=回数+タイミング、という点が生物学的にも支持されています。
実践:教材を「やり尽くす」ための日本版ポイント
① 回数を意識する
教材は「1回だけで終わり」ではなく、最低3〜5回以上回すことを目安にします。反復回数が多いほど定着しやすいという国内研究の示唆があります。
② 間隔をつくる
「今日・明日・数日後・1週間後」のように、反復の間に時間をあけることで記憶が強くなります。関西大学の研究で提示された手法がその根拠です。
③ 見える化と自己調整
教材を回すごとに「どこが分からなかったか」「何が怪しいか」を記録しておくと、自己調整学習(学び方を自分で最適化する)につながります。これは「記録すると成績が上がる」という研究からも支持されています(例:メタ認知研究)。
④ 小さな理解から広げる
苦手な問題や分野は「まずは部分だけ理解する」→「それを関連知識に広げる」→「再挑戦で完全化する」という構えが有効です。難問を放置せず、小さな突破口を作ることで、回転学習がスムーズになります。
今日から始めるためのチェックリスト
- 今日扱う教材・範囲を決め、3回以上回す予定を立てる
- 初回終了後、2〜3日後に再挑戦する日程をカレンダーに入力
- 解けなかった箇所をメモし、「次回必ず理解する」という意思をもつ
- 教材1冊を終了したら「回数・所要時間・正答率」を簡単に振り返る
- 疑問点が残ったら、次回回転時に「部分理解」に絞って手を動かす
まとめ
日本の教育・記憶研究では、「量」=時間をただ増やすこと以上に、反復の回数・間隔・振り返りの質が学習成果を大きく左右することが明らかになっています。
教材をやり尽くすとは、単に終わらせることではなく、“理解が定着するまで回す”こと。今日から少しずつ、“1冊をやり切る”学び方に切り替えてみてください。
参考リンク
- 学習効率がぐんぐんアップ!アクティブリコールと間隔反復(マイナビ子育て) — https://kosodate.mynavi.jp/articles/38937 マイナビ子育て|夫婦一緒に子育て
- 短期記憶を長期記憶へ移行する方法(大阪教育大学) — https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/45-11.pdf f.osaka-kyoiku.ac.jp
- 復習間隔を少しずつ広げていくことは長期的な記憶保持を促進…(関西大学) — https://www.kansai-u.ac.jp/fl/publication/pdf_department/19/35nakata.pdf 関西大学
- 反復学習が記憶を蓄える神経細胞集団を形成するメカニズムを解明(医学研機構) — https://www.igakuken.or.jp/topics/2018/1204.html 医学研
- 繰り返し学習の有効性について(2023刊) — https://seiyogakuin.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2023/03/gakutyo1.pdf 仙台青葉学院
お問い合わせ
無料体験のご依頼や、受験生活でのご相談、その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください
フォームでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
受付時間 10:00~18:00
(土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く)