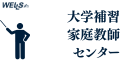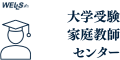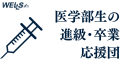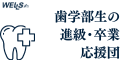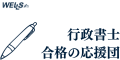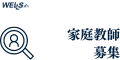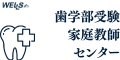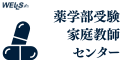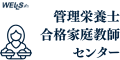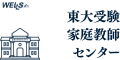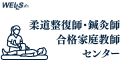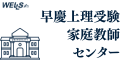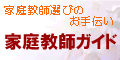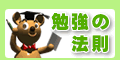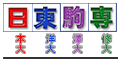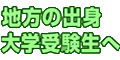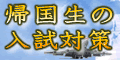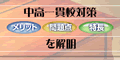勉強は何時間すればよいか?
受験生から最も多い質問のひとつが「1日どのくらい勉強すればいいですか?」です。
しかし、明確な“正解時間”は存在しません。
合否を分けるのは、時間の「長さ」ではなく、時間の中身(質)と継続の安定性です。
🎯 結論:量も質も大事。だが“質が先”
「量」=学習時間。
「質」=その時間にどれだけ脳が学習しているか。
質の高い勉強とは、集中・理解・記憶・フィードバックの4つの要素がそろった状態を指します。
最新の学習科学では、同じ時間でも“質の高い勉強”は3倍以上の効果を持つことが確認されています。
📚 エビデンス
- Roediger & Karpicke (2006): 「テスト効果(retrieval practice)」により、同じ学習時間でも“思い出す練習”を含めると定着率が2〜3倍向上。
- Cepeda et al. (2008): 「間隔学習(spacing effect)」で、復習の間隔を空けた方が記憶保持が20〜50%向上。
- Dunlosky et al. (2013): 「メタ分析による有効学習法」でも、“繰り返し読むだけ”より“自己テスト+分散練習”が最も効果的と報告。
🧩 勉強の“質”を高める4原則
① 思い出す(テスト効果)
ノートを読むより、「自分で思い出す」練習が記憶を強化します。
模試や過去問はもちろん、ミニテスト形式の復習を日常に組み込みましょう。
- 教科書を閉じて“口で説明する”
- 解答を隠して“再現する”
- 模試後に“間違えた理由”を言語化する
→ 記憶の呼び出しで、脳が「重要情報」として再保存します。
② 間隔をあけて復習する(分散効果)
一気に詰め込むより、時間を置いた反復の方が定着率が高いです。
復習の黄金リズム:
翌日 → 2日後 → 1週間後 → 2週間後 → 1か月後
これに沿って計画を組むと、忘却曲線を効果的に打ち消せます。
③ フィードバックを受ける
人は自分の理解度を過大評価しがちです(Dunning–Kruger Effect, 1999)。
必ず誰か(教師・チューター・友人)に説明し、間違いを修正する機会を設けましょう。
“正答を当てる”より、“誤りを直す”方が脳の可塑性を強く刺激します。
④ 集中環境を整える
集中の質を左右する最大要因は「中断の少なさ」です。
スタンフォード大学の研究(Mark et al., 2015)では、
「中断を受けた学習者は、集中を取り戻すまでに平均23分を要する」
と報告されています。
そのため、スマホ通知をオフにする、タイマー学習を取り入れる、
“90分以内のブロック勉強”が最も生産的です。
📈 勉強時間は“徐々に増やす”
質を保つには、量を段階的に伸ばすことが必要です。
いきなり長時間にするのではなく、習慣として定着させることを優先。
- 行動変容理論(Prochaska & DiClemente, 1983)
「小さな成功体験」を積み重ねた方が継続率が高い - Stanford行動デザイン研究(2020)
“少しずつ負荷を増やす学習者”は中断率が30%低い
🧠 質 × 量の最適バランスとは
| 学習時間 | 質の指標(集中・理解・記憶) | おすすめ構成 |
|---|---|---|
| 1〜3時間/日 | 高密度(集中重視) | 苦手潰し+小テスト |
| 4〜6時間/日 | バランス型 | 苦手+得意維持+復習 |
| 7〜9時間/日 | 量重視(要休憩) | 模試形式+復習サイクル |
| 10時間以上 | 効率低下リスク | 睡眠・運動をセットで管理 |
量だけを追うと、脳の疲労により記憶効率が下がる(Yerkes–Dodson Law, 1908)ため、
「集中できる時間を積み重ねる」視点が必要です。
✅ まとめ
無理のない量でスタートし、継続と改善を軸に。から動くこと。苦手が減り、得意が増えれば、学習時間は自然に意味を持ち、成果に直結します。
「量」=走行距離、「質」=エンジン効率。両方が必要。
勉強の“質”は、「思い出す」「間をあける」「フィードバック」「集中環境」で決まる。
📚 参考文献・研究
- Roediger HL, Karpicke JD. Psychological Science, 2006
- Cepeda NJ et al. Psychological Science, 2008
- Dunlosky J et al. Psychological Science in the Public Interest, 2013
- Mark G et al. International Journal of Human-Computer Studies, 2015
- Prochaska & DiClemente, Stages of Change Model, 1983
- Yerkes & Dodson, Journal of Comparative Neurology & Psychology, 1908
- Walker M. Why We Sleep, Scribner, 2017
お問い合わせ
無料体験のご依頼や、受験生活でのご相談、その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください
フォームでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
受付時間 10:00~18:00
(土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く)