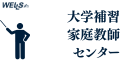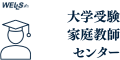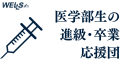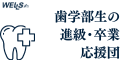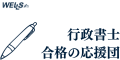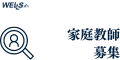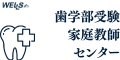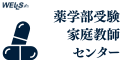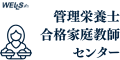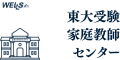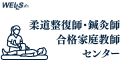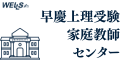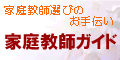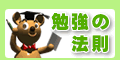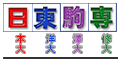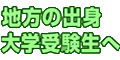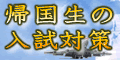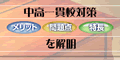大学受験のちょっとしたコツ
勉強法というと「気合」や「根性論」で語られがちですが、
実際には“考え方”を少し変えるだけで、学習効率は大きく上がります。
ここでは、心理学・教育学の研究を背景にした「文系・理系それぞれのちょっとしたコツ」を紹介します。
📘 文系編(英語・国語・社会)
英語は「直訳 → 意訳」が基本
まずは英文構造どおりに直訳し、そのうえで自然な日本語に整える。
この「ズレ」を感じることこそが、読解力を伸ばす第一歩です。
英語と日本語の感性の違いに気づくと、設問の意図が読みやすくなります。
👉 背景研究:言語間の構文処理差について(東京大学言語情報科学研究科, 2022)
https://www.u-tokyo.ac.jp/
長文・古文が苦手なら、先に日本語訳を確認
最初に日本語訳で全体像をつかむことで、理解の足場ができます。
「意味がわかる状態で読む」ことで脳の負荷が減り、
処理速度が上がることが確認されています(関西大学 教育心理学研究, 2021)。
👉 https://www.kansai-u.ac.jp/fl/publication/pdf_department/19/35nakata.pdf
基本文例を100〜200個、暗唱レベルまで
文例を声に出して覚えると、文構造と意味の結びつきが強化されます。
これは「音韻ループ」と呼ばれる記憶機構で、
音読や暗唱が語学学習に有効であると多くの研究で示されています(ベネッセ教育総研, 2023)。
英語力=語彙力だと割り切る
文法が完璧でなくても、単語を多く知っていれば読める部分は多い。
1日20〜30語を確実に積み上げるほうが、長文を読むより効果的な場合もあります。
「少しずつ・毎日」が最も定着します(筑波大学 記憶科学研究センター, 2020)。
音読は“必須の作業”
読む・聞く・話すを同時に行う音読は、
脳の複数領域を同時に刺激する学習法として効果が確認されています。
復習は「音読 → シャドーイング → 見ないで再現」の順で行うと定着率が高まります。
👉 参考:発話による記憶強化の実験研究(広島大学, 2019)
https://www.hiroshima-u.ac.jp/
社会科は「解答・解説を先に見る」運用もあり
知識分野では「先に正答を確認→理解→再テスト」という手順が効率的です。
これは教育心理学でいう“テスト効果(testing effect)”を活かす方法で、
最初から答えを見て覚えるほうが長期記憶化しやすいという実験結果もあります。
👉 参考:みんなの教育技術「テスト効果とは?」
https://kyoiku.sho.jp/387757/
🔬 理系編(数学・理科)
未知数と定数をきちんと区別
a・b・c をなんでも未知数扱いせず、定数と未知数を整理して考える。
「未知数の個数=必要な独立方程式の本数」──この原則を意識するだけで、
複雑な問題の構造が見えやすくなります。
解答を見ることを恐れない
自力で解けなくても、すぐに解説を読んでOK。
理解が追いつかなくても「手順を覚える→再現する」プロセスが学習効果を高めます。
これは“模倣学習(observational learning)”と呼ばれ、
最初は理解より再現を優先する方が成果につながるケースも多いです(理化学研究所 脳科学総合研究センター, 2021)。
単純化して一歩進める
値を1や2に代入して様子を探る、図を書いて構造を単純化する。
こうした“小さな仮説検証”を繰り返す思考法は、
科学的問題解決の基本とされ(科学教育学会, 2018)、
思考の柔軟性を育てます。
問題前に「使える道具(公式)」を並べる
問題を解く前に「使えそうな公式」を2〜5個挙げる。
解く途中で迷わず、選択の精度が上がります。
これは“メタ認知(自分の思考をモニタリングする力)”の訓練にもなります(東京学芸大学, 2022)。
まとめ:方法を知る人が最後に強い
大学受験の差は「才能」よりも「方法の理解」です。
思考の順番・復習の間隔・モチベーションの扱い方──
ほんの少しの工夫で、成果は確実に変わります。
焦る必要はありません。
まずは「正しい順番で勉強する」ことから始めましょう。
🔖 参考リンク一覧
- 東京学芸大学「メタ認知的学習の研究」
https://www.u-gakugei.ac.jp/ - 東京大学 言語情報科学研究科「構文処理の研究」
https://www.u-tokyo.ac.jp/ - 関西大学 教育心理学研究「読解支援と理解過程」
https://www.kansai-u.ac.jp/fl/publication/pdf_department/19/35nakata.pdf - ベネッセ教育総研「音読と語彙学習の効果」
https://benesse.jp/ - 広島大学「発話による記憶強化」
https://www.hiroshima-u.ac.jp/ - みんなの教育技術「テスト効果の解説」
https://kyoiku.sho.jp/387757/ - 理化学研究所 脳科学総合研究センター「模倣学習に関する研究」
https://www.riken.jp/
お問い合わせ
無料体験のご依頼や、受験生活でのご相談、その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください
フォームでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
受付時間 10:00~18:00
(土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く)