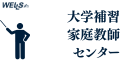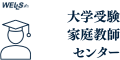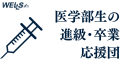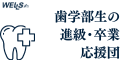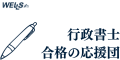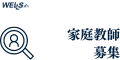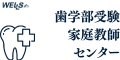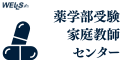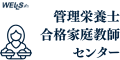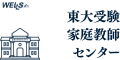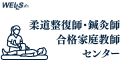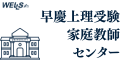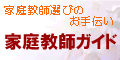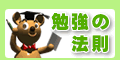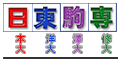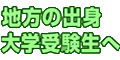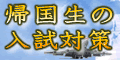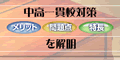過去問を制するものが早慶上理を制する
過去問は「手応えを測る道具」ではなく、志望校を理解し、合格までの最短ルートを描くための研究資料です。上位大学では出題傾向が明確で、得点源のパターンが毎年似ています。そこを“読める”受験生が、合格ラインを正確に取りにいきます。
🧭 過去問で見えてくる「大学の思考」
難関大学の出題は、単なる知識ではなく「思考の再現力」を問います。
つまり、大学が何を“考えてほしいか”を読み取ることが、合格の鍵です。2025年度入試でも、資料・図表・複数資料を組み合わせた問題の比率が高まりました。 キャリアタス教育+1
まず最初に確認すべきは次の6項目です。
- 教科別・大問別の配点構成
- 合格最低点・合格者平均(年度ごとの推移)
- 出題形式(記述/マーク、和訳・英作・要約など)
- 頻出単元と出題比率の偏り
- 難易度の波(差が出やすい設問配置)
- 制限時間と、1問あたりの理想処理時間
この6項目を“大学の設計図”として捉えると、
「敵を知る」から「戦える受験」に変わります。
👉 参考: [大学入試センター「出題傾向分析」] (https://www.dnc.ac.jp/)
🔍 過去問の使い方:上位大学向けの「研究プロセス」
2025年度版として特に意識したいのは、出題の“変化”に伴う研究力です。
- 傾向の把握(読む)
直近3〜5年を通読し、設問の型・テーマ・論点を整理。2025年の共通テスト分析でも、図表+資料+読解力重視の傾向が報告されています。 zkai.co.jp+1 - 配点と形式を一覧化
Excelやノートに「配点表」「形式表」を作成。 - 仮得点計画の設計
大問ごとに「取る設問・捨てる設問」を明文化。 - 模試環境での初回演習 → 分析メモ作成
自己採点後、「なぜ点が落ちたか」を5分類(知識/読み違い/計算ミス/時間切れ/戦略ミス)で整理。 - 原因別対策を設計
「教材×回数×締切」をセットでタスク化。 - 再現トレーニング
同年度の問題を「48時間後→1週間後→1か月後」に再挑戦。記憶定着に最も効果的とされる「間隔反復」の活用です。 スタディコーチ|難関大学・難関高校合格のための個別指導塾+1
⚙️ 戦略を立てる思考法
早慶上理レベルになると、「努力の量」より「得点設計の精度」が勝敗を分けます。以下を意識してください。
- 高配点科目から逆算して得点源を作る。
- “取り切る設問”と“触れない設問”を事前に決めておく。
- 毎回同じ順番・時間配分で解答(自習時からルーチン化)
- 記述・英作文は採点観点を抜き出してテンプレ化(構文数、論点、減点条件)
このように、過去問は“再現力を鍛える訓練場”となります。資料を読み解き、設問傾向をつかみ、自己の弱点を見える化していく。これが「点数を作る戦い」です。
📚 年度別の使い分け(早慶上理志望向け)
| 目的 | 年度 | 活用法 |
|---|---|---|
| 精密演習 | 直近3〜5年 | 満点再現を目指す反復練習 |
| 型の研究 | 6〜10年前 | 頻出テーマ・構成の変化を分析 |
| 研究期 | 夏〜秋 | 傾向と配点の分析中心 |
| 実戦期 | 秋〜冬 | 時間配分・再現トレ中心 |
💡 よくある誤解と修正法
| 誤解 | 修正の視点 |
|---|---|
| 「過去問は直前期だけ解けばいい」 | 夏から研究を開始、秋には反復へ移行 |
| 「1回解けばOK」 | 年度1本を複数回転させて記憶定着を図る |
| 「解説を読むだけで理解できる」 | 次回同じ問題で「何点取れるか」を数値化して記録 |
| 「参考書で補強しよう」 | 過去問で落とした原因に直結する教材だけを選ぶ |
📖 記録テンプレート(例)
| 年度 | 科目 | 配点 | 目標点 | 実得点 | 失点原因 | 対策教材・締切 | 再現日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 英語 | 100 | 80 | 65 | 構文ミス・時間不足 | 英構文100本 2回転/11月10日 | 48時間後・1週間後・1か月後 |
このように“記録の定型化”を行うと、学習がプロジェクト管理に変わります。感情任せではなく、データに基づいた戦略が合格を引き寄せます。
🏫 志望校決定への応用
同じ偏差値帯でも、早慶・上智・理科大間には配点・形式・論点のクセがあります。
例として:
- 慶應経済:英語・小論文比重大
- 早稲田法:法律文・論理読解中心
- 上智文:語彙精度+要約力
- 理科大:思考型計算+処理スピード
このような「大学のクセ」を把握することが、相性の良い大学に絞る戦略的思考につながります。
📦 過去問の入手先(早慶上理志望向け)
- 赤本(教学社):最もスタンダード。出題傾向分析付き
- 青本(駿台):解説が詳しく、上位層向け
- 緑本(Z会):要約・英作文分析が充実
- 黒本(河合塾):模試形式で実戦演習に最適
- 白本(代ゼミ):分野別解説で苦手補強に向く
※年内(11月末まで)に確保が安全です。
🧠 最後に:過去問は「相手を知り、己を鍛える鏡」
孫子の言葉にあるように──
「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」
過去問は、大学を知る鏡でもあり、同時に自分の成長を映す鏡でもあります。
解くたびに、自分の弱点が「伸びしろ」に変わっていきます。
早慶上理を目指すのであれば、量より分析。
1問1問に意味を見つける学習こそ、最短ルートです。
📚 参考リンク
- 大学入試センター「出題傾向分析」
- Z会 2025年度大学入学共通テスト 科目別分析速報 zkai.co.jp
- 「2025年度最新版!過去問の使い方徹底解説」研究記事 スタディコーチ|難関大学・難関高校合格のための個別指導塾
お問い合わせ
無料体験のご依頼や、受験生活でのご相談、その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください
フォームでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
受付時間 10:00~18:00
(土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く)